▼2006年政治展望2006/02/12 21:52 (C) さがえ九条の会
▼こんな記事もめっけ!〜五十嵐仁の転成仁語より〜
「講演と対談」には、40人ほどの方が出席されました。このHPを読み、「五十嵐というのはどんな顔をしているのか」と見に来て下さった読者の方も何人かおられたようで、声をかけていただきました。 このHPを読んでおられる方だと、すぐに話が通じます。初対面なのに、旧知の方のような不思議な感覚を味わいました。 読者の方からは、このHPを読むのを楽しみにしていると励ましていただきました。ありがとうございます。この場を借りて、お礼申し上げます。 小林さんとは、直接お話しするのは初めてでした。ただ、2004年秋に札幌で開かれた政治学会の分科会での報告を聞いたことはありますし、そのことは拙著『活憲』第1部第1章のなかの「『非武装論』と『墨守・非攻論』の間」(52頁以降)に書きました。 小林さんの方も私のことはご存知で、この政治学会の感想についても読まれていたそうです。このとき、共通論題Ⅱ「グローバルパワーとしてのアメリカ内政構造」について、私は「内容的にも期待はずれで、門外漢の私であっても多くの不満と問題点を感ずるものでした」と苦言を呈しました。 小林さんは、このとき企画委員でこの共通論題を企画されたそうです。私の書いたことに反論されるのかと思いましたら、「私も全く同感だったんですが、企画したものが文句を言うわけにはいきませんから、率直に問題を提起していただいて、かえって有り難かったです」と言われ、恐縮してしまいました。 ところで、拙著では、小林さんの「墨守・非攻論」について、「『保持』が許される『武力』の水準については何も述べてはいません。たとえば、今日の自衛隊はその水準を超えているのでしょうか、いないのでしょうか」(54頁)と書きました。これについて「ご意見をうかがいたかった」(55頁)と……。 今回の「講演と対談」は、このような点についてご意見をうかがう絶好の機会でした。結論を言えば、この点でも小林さんと私との違いはほとんどありませんでした。 その他の点でも、ほとんど違いがありません。ただし、小林さんは、同じ卯年で私よりも一回り若く、それだけにエネルギッシュで行動的であり、現状についてのより強い危機感を表明され、より鋭い告発を行いつつ、地球平和公共ネットワークの代表を務められるなど、現状打開のための具体的な行動に取り組まれています。 小林さんは、その著『非戦の哲学』(ちくま新書、2003年)で、「テロ特措法はもはや解釈改憲ですらなく、争う余地のない完全なる憲法違反行為であり、そのようなことを行う政府は、すなわち『クーデター』を行うことになる」(112頁)と書かれています。まして、イラク特措法やそれに基づいてイラクに派兵された自衛隊を合憲であると考えられるはずがありません。 私は、政治学会の時点ではこの本を読んでおらず、したがって、小林さんのこれほどの厳しい見方を知りませんでした。今回、このような質的な意味だけでなく、量的な水準においても、自衛隊の現状は自衛力の範囲を超えているので縮小をめざすことを明らかにされました。 ということであれば、小林さんの「墨守・非攻論」と私の「気休め防衛論」との違いはほとんどなくなります。この場を借りて、拙著の記述を訂正させていただきます。 特に重要だと思ったのは、憲法九条については時代状況に応じての解釈が可能であり、憲法制定過程においてもそれは否定されていなかったという指摘です。この点で、「憲法原理主義」の立場を排するということ、そのような解釈においても、許されるのは「武力」の保持であって「軍事力」を持つことは許されないと主張されました。 つまり、「武力」の範囲にとどまる「自衛隊」でなければならず、「軍事力」を持つ「自衛軍」(日本軍)であってはならないというわけです。このような「武力」と「軍事力」との厳密な使い分けは、「政治哲学」や「公共哲学」を専攻されている研究者の面目躍如たるところがあります。 私は、拙著『活憲』で、「九条によってもたらされたさまざまな制約」について指摘し、九条改憲はその制約を取り払うことになると指摘しました。このような制約によって「軍事力」として機能することを抑制されているのが「武力」としての自衛隊だということになります。 今日の自衛隊は、長年にわたる「実質改憲」の積み重ねによって、質的にも量的にも「九条の制約」を部分的に踏み越えています。「武力」としてのあり方をはみ出すようになってきているということになるでしょう。 その「制約」を全面的に取り払い、アメリカにとって「使い勝手の良い軍事力」に変身させようというのが、九条改憲の狙いです。それを押しとどめるだけでなく、気休め程度の「武力」にまで縮小させるというのが、「活憲」の課題だということになります。 小林さんのお陰で、大変、理論的にスッキリさせることができました。これが、この「講演と対談」に出席した私の大きな収穫でした。 2006/02/15 19:30:かくれ「さがえ九条ファン」
|
▼100advertising▼ranking
|
|
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
|
|
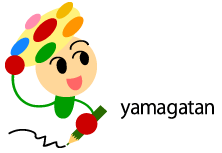
『全国商工新聞』(2006年1月9日付)
今年は、大変厳しい年になる。先の総選挙で大勝した与党が、全面的な攻勢に出ることが予想されるからである。
国政選挙がないから、悪政に対する国民の審判を恐れる必要がない。野党第一党の前原民主党は「提案路線」に転じ、悪政へのブレーキ役を放棄してしまった。9月に辞めるつもりの小泉首相は、「イタチの最後っ屁」で、やりたい放題やるだろう。
こうして、構造改革による「痛み」が、大挙して押し寄せてくるにちがいない。小泉首相の“悪政商店”が「閉店セール」を開くようなものだ。これを押し返し、翌年に向けての展望を切り開くことができるかどうかが06年の課題となろう。その焦点は、07年春のいっせい地方選挙、夏の参院選に絞られることになる。
生活を破壊する嵐がやってくる
政府・与党は、来年度に向けて所得税と住民税の定率減税廃止と給与所得控除の縮減、配偶者・扶養控除の廃止を図ろうとしている。消費税も、07年度からの2けたへの引き上げが画策されている。庶民の生活を直撃する大増税が、嵐となって吹き荒れるにちがいない。
「福祉破壊」もいっそうすすむ。年金の給付削減と負担増、障害者福祉での個人負担増、介護保険での自己負担増に続いて、来年度は、高齢者の医療費負担が引き上げられる。歳出削減のための社会保障関係費の見直しもある。「三位一体改革」でも、義務教育と生活保護への国庫負担を削減し、国の責任を放棄しようとしている。
「お金がなく、制度を維持できない」というのがその理由だが、800兆円弱にまで長期債務を増やしてきたのは、小泉首相を含む歴代の自民党政権である。失政のツケを国民に払わせるような暴挙を許してはならない。
大増税と「福祉破壊」は国民の可処分所得を減らして生活不安を増大させ、内需を冷え込ませることになるだろう。9兆円の負担増によって景気回復の芽をつんだ橋本内閣の愚を繰り返そうというのだろうか。軍事費や公共事業の無駄をなくし、収益増で笑いが止まらない大企業や金持ちから税金を取り、景気回復によって税収増を図ることこそ、本来のあるべき姿だろう。
進路が問われる従米・属国路線
結党50周年で改憲案を発表した自民党は、1月の国会に国民投票法案を提出するとしている。年明け早々から、憲法をめぐる攻防が始まることになろう。併せて、在日米軍の再編・強化と自衛隊との融合・一体化が進められようとしている。世界のどこででも米軍と一緒に戦える軍隊に変えるためである。
小泉首相の従米・属国路線は、靖国神社参拝などもあって周辺諸国の警戒感を高め、関係悪化を招いている。もし、最後の置き土産として8月15日に靖国神社を参拝するようなことになれば、日本の外交は決定的なダメージを受けるだろう。その前に、「死に体」へと追い込まなければならない。
日米安保条約は日本の安全破壊
今年は、イラクからの自衛隊撤退も現実的な問題となろう。日米間の「安全保障」体制が平和と安全を保障しているのかが、本格的に問われる年になる。安保があるから日本が狙われる。それは「安全保障」ではなく「安全破壊」体制なのだという本質が、白日の下にさらされるにちがいない。
平和憲法を変えるのか守るのかという問題は、日本の進路を問う重要な争点として06年の底流を流れ続けるだろう。必要なのは、憲法を「変えるより活かす」ことである。そう論じた拙著『活憲―「特上の国」づくりをめざして』を、先ごろ上梓した。強まる改憲攻勢をはねかえすだけでなく、反転攻勢のための“武器”として活用していただければ幸いである。